
メガネを愛した人たちへ─l.a. Eyeworksが教えてくれたこと
私がメガネ屋になったのは1999年のことだ。90年代が終わりを迎え、2000年のミレニアム、2001年から始まる新世紀に期待を抱いていたかと言えば、むしろ真逆だった。あの頃の日本経済は、バブル崩壊後の長引く不況からまだ抜け出せず、厳しい状況が続いていた。雇用情勢は悪化の一途をたどり、完全失業率は過去最悪の水準に達し、有効求人倍率も過去最低というまさに底辺の時代だった。
しかしその一方で、メガネ業界はアラン・ミクリをはじめとするブティックブランドの台頭により活気を帯びていた。「コンセプトショップ」と呼ばれる個性を打ち出したメガネ店は繁盛し、全くメガネと縁のなかった人たちも参入し、特定のブランドを揃えて並べるだけで「コンセプトショップ」の一員として認められた。今でもその当時の名残は消えずに残っているように感じるし、最近でもメガネの技術が十分でないまま、突然メガネ屋として独立する若者が増えている気もする。
1999年当時の若造甚だしい頃だって同じことを感じていたんだから、ジジィになって一過言申し上げたいわけではない。
CHECK!!
アメリカ行脚で見つけた眼鏡屋としての原点

l.a.Eyeworksの創業者であるゲイ・ゲラルディーさんとバーバラ・マクレイノルズさんが亡くなったと、プラトーイの石渡氏から連絡があった。2016年、私がGROOVERをアメリカに売り込んだ際、招待者限定のVISION EXPO WEST「SWEET」へ招いてもらい、ゲイさんと盟友のマーゴさんを石渡さんから紹介していただいた。
当時、私はGROOVERをアメリカ市場に売り込もうと、メガネの見本市に出展するだけでなく、成果がなかなか上がらないためカナダや北米のメガネ店へ飛び込み営業を積極的に行った。インターネット全盛の時代において、日本のブランドが直接飛び込み営業をする例はほとんどなく、「日本人が直接営業に来るのか!」とどこへ行っても驚かれ、話だけは聞いてもらうことが出来た。2019年のVISION EXPO EAST(ニューヨーク)でようやく黒字化を達成したが、その前の3年間は思うような成果が得られず、精神的にも資金的にも非常に厳しい時期が続いた。
1999年当時、多くのブティックブランドが日本代理店を通じて紹介されていた中で、l.a.Eyeworkのカラフルでポップなデザインはひときわ異彩を放っていた。ベルギーのTHEOやフランスのlafontなど、ヨーロッパの気鋭デザインも存在していたが、保守的で「黒とべっ甲しか売れない」と言われていたアメリカ市場から届くl.a.Eyeworkの新しいスタイルを雑誌で見るのが楽しみだった。
当時、私は父の店を手伝うように継ぐのだが「時計・メガネ・宝石」の兼業店から、メガネ専門店へとリニューアルした。メガネの仕事の経験がなかった自分がなぜメガネ専門店にしたのか、今でもはっきりとは分からない。ただ、当時の状況下で、時計や宝石に比べて「コンセプトショップ」のおかげでメガネだけが突破口となる可能性を見出せたのかもしれない。父の店は不況の煽りをモロに受けており、経営は火の車だった。
そんな日本の大不況の最中にあって、メガネのデザインは明るかった。
ヒッピーカルチャー全開!L.A. Eyeworksを追いかけた3年越しの旅

2016年、ラスベガスでゲイさんとマーゴさんにお会いした際、そのポップなデザインの源泉がヒッピーカルチャーにあることをすぐに理解した。本当にヒッピーカルチャー全開で、一目でその世界観が伝わってきた。いつか本拠地のロサンゼルスで取材したいと願い続け、2019年夏のアメリカ西海岸出張の際にようやく実現した。正直なところ、その取材内容は公開せず自分だけのものにしたい気持ちもあったが、ゲイさんがl.a.Eyeworksについて語ってくれる貴重な機会だったので、相応の形で世に出すべきだと考えた。
私は香港のメガネ雑誌「V MAGAZINE」の日本発行権を取得し、2015年にはネコ・パブリッシングの協力を得て「V MAGAZINE JAPAN」を創刊した。V MAGAZINEのボスであるケイメン氏に直接交渉して日本での創刊にこぎつけたものの、編集に私の意向が十分に反映されないことも多く、自費で取材した内容を無償提供することには抵抗があった。それでも、多くの人にその内容を知ってもらいたいという思いから、自我を抑えて協力したのだった。その後、多くの海外取材記事を「V MAGAZINE JAPAN」に無償提供したが、これはこれで良かったと今は思っている。

当日、ゲイ・ゲラルディーさんが取材に応じてくれた。l.a.Eyeworksはゲイさん、バーバラさん、マーゴさんが中心人物の3人で、バーバラさんは途中l.a.Eyeworksを離れた時期があるそうで、マーゴさんは創業メンバーではないそうだ。ゲイさんが最重要人物なのである。
この時の取材の一部は、2019年秋のV MAGAZINE JAPANの記事として掲載された。この文章は今読んでも胸を打つ。アイウェアジャーナリストの実川治徳さんが書いた文章をそのまま引用する。
ここカリフォルニアはアイウェアに対して保守的だが彼女のクリエイションは前衛的かつ、ウェアラブルなデザインだ。「あははっ! ありがとう。でも背中がムズムズするわ(笑)。バーバラと私は常々、アイウェアはレンズを固定するための道具ではなく、コミュニケーションのキッカケを作ってくれる、とても偉大な“コミュニケーター”だと思っているの。この眼鏡(自身の黄色い眼鏡を指して)を掛けていたら怖い人には見えないし、話し掛けやすいでしょ? それが私たちのアプローチ。アイウェアに情熱を持っている人なら、皆知っていると思う」。
そんなホットなアイウェアたちがズラッと並ぶのが、まるで“宇宙船乗り場”を彷彿とさせる旗艦店。2002年にローカルの建築家、ニール・ディナーリによって設計された未来的な同店は21世紀のl.a.Eyeworks を担う、ブランドのオンリーショップとなる。路面店といえばウィンドウディスプレイが定石だが、彼らのショップではあえてそれをせずに短く、それでいてウィットに富んだ標語が掲げられている。そして中を覗いてみないと何があるか分からない。「時に私たちは、その時々に興味の湧いたものや政治的なメッセージ、心地いいコトやモノをウインドウに掲げます。そして来てくれる人とアイデアを交換し合ったり、知らないものやことを与え教え合ったり、オファーし合ったりするの。それから日中はリテールスペースだけど、お店って夜は何もないでしょ? そこで閉店後はグランドピアノを入れてコンサートを開いたり、映画鑑賞しながら香水を楽しんだり、詩の朗読をしたり、と楽しいイベントを開催しているのよ。そう、月曜日は“マジックマンデー”と題して手品も。そんなイベントが窓越しに見えれば人が集まって、自然と今まで足を踏み入れたことのないアイウェアの世界も知ることができる。クールじゃない? だからお店って楽しい。人生は楽しまなきゃね」。彼女にとってのショップは、モノを売るだけのセールスマシーンではなかった。さまざまなアクションが境界なく広がる、言うなればアイデアマシーンだった。
V MAGAZINE JAPAN 2019 秋号より引用
90年代当時から一つだけ疑問があった。「Eyeworks」というブランド名が、少しマッチョすぎるのではないか? ということ。この答えはインタビュー記事にもあるが、1979年の創業当時、メガネを仕入れる資金がなく、面白いことをやるには既存のメガネを改造するしかなかったそうだ。その工房は、映画『ブレードランナー』に登場する〈目玉工場〉として使われた。まさに、眼鏡を「作り」、そして「遊ぶ」という意味での “Eyeworks”こそがブランド名の由来だった。
心を奪われた言葉たち──L.A. Eyeworksの標語とそのスピリッツ

特筆すべきは、 l.a.Eyeworksが掲げる標語がいちいちカッコいい。
A face is like a work of art. It deserves a great frame.
「顔は芸術作品のようなもの。素晴らしいフレームにふさわしい」
2019年の取材時、店頭には「FACE FORCE」という標語が掲げられていた。このフレーズは後に、メガネナカジマや陽ハ昇ルの店舗におけるメガネ作りの「意気込み」として勝手に受け継がさせて頂いた。
2011年のIOFTでGROOVERの卸事業を始めた時にも
「メガネは掛ける人の人生そのものである」
というコンセプトを掲げた。これはl.a.Eyeworksの「A face is like a work of art. It deserves a great frame.」に多大な影響を受け、自分の言葉で一番ブランドとして幹となる信念を掲げたかった。今でもこのスピリッツが全ての行動原則になっている。
うがった見方かも知れないが、ありきたりのデザインで産地偽装しPRにお金を掛けて「売れるブランド」にした中身のないブランドを、この20年くらい世界のメガネ店やバイヤーは持て囃したと思う。
近年メガネブランドがファンド化し、売却に成功したデザイナーやオーナー達は次々と去っていった。最初からそれを目的としていた人も多い。
その結果、本気でメガネと向き合うデザイナーや、熱意を持ったバイヤー、ショップは世界的に減少した。もはや、スピリッツあるデザイナーは世界中を探しても数えるほどしか存在しない。だからこそ私の中ではゲイさんのようなメガネ人は輝いていた。
ゲイさん、バーバラさん、そしてマーゴさんの歩んできたメガネ屋としての人生に、心から最敬礼し、深い敬意を捧げる。
note.でも連載中です。
中島 正貴
有限会社スクランブル 代表取締役
1999年にメガネ業界に入る。新宿の紀伊国屋にあった三邦堂(閉店)でドイツ式両眼視測定を学ぶ。2006年よりメガネブランド「GROOVER」を立ち上げ、国内外の展示会へ出展する。2011年より世界初のレンズカスタムレーベル「GOODMAN LENS MANUFACTURE」を立ち上げる。2016年より世界のアイウェアシーンで有名なアイウェアマガジン「V.MAGAZINE」、アイウェアエキシビジョン「V.O.S」の日本開催権を取得。ネコ・パブリッシングの協力により「V.MAGAZINE JAPAN」の刊行と、「V.O.S TOKYO」を開催する。2021年には日本発のスポーツサングラスブランド「XAZTLAN」を発表。2022年、メガネの「ホントにミニマムな国際展示会RAMBLE」を7年ぶりに復活。2023年、5坪のメガネ屋「陽ハ昇ル GROOVER×XAZTLAN」を表参道にオープンさせるなど精力的に活動中。
職歴
・メガネナカジマ代表
・陽ハ昇ル GROOVER×XAZTLAN オーナー
・GROOVERデザイナー
・GYARD主宰
・XAZTLAN(ザストラン) CEO
・東京セイスターグループ理事





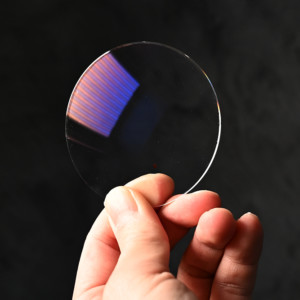






この記事へのコメントはありません。